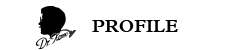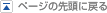テーラーメイド治療を実現する『医療判断医』
 |
自分にとって最善の医療を実現してくれる「主待医」 テーラーメイド治療を実現する『医療判断医』 |
花かすみとけい 2003.6.1 八峰出版 |
普段から自分の健康を相談できるプライベートドクター
自分の病気にはどの医療施設や医師が適切なのだろうか。また、自分の健康状態をじっくり相談できる医師がいたなら、どんなにか心強いことだろう。
そんな願いを実現してくれる医師、それが医療判断医であり、「主治医」ならぬ「主侍医」というプライベートドクターです。
では、どういったことを行っているのでしょうか。
医療がオーケストラなら、医療判断医は指揮者の役目
医療判断医‥。
聞き慣れない言葉ですが、これは寺下謙三先生の肩書きの一つ。患者が最善の医療を選べるよう支援することを役目とした医師だそうです。
患者の症状から、どの専門外来を受診したらいいのか。それが、がんであるなら、薬を使う治療がいいのか、それとも外科手術の方が適切なのか。また、手術を行うのであれば、臓器をすべて摘出するのか、がんを中心に切るのか。あるいは東洋医学でいくのか‥。
当事者でなければ計り知れないような苦悩を抱えて決断に迷う患者やその家族に対し、医療判断医として先生はより適切な医療機関や医師、治療法などをアドバイスしておられます。
内科医は最善の薬物治療に専念し、外科医は最善の外科治療を目指すことが多いもの。しかし、知人の紹介や評判を頼りに、意を決して出向いた先の担当医の説明が、決して十分とは思えない場合もあるでしょう。「患者さんの心の変化、職業や家族、信仰している宗教にまで配慮しなければ、本当の意味での治療計画は立てられません」とも。心のケアから生活面でのアドバイスやサポートまで、医療判断医・寺下先生が行っておられることは、これまで患者が切に望んでいたことそのものだといえます。
先生は、「医療をオーケストラに例えるなら、医療判断医は指揮者役だ」といわれます。先生が、さる高名な指揮者のご令嬢から聞かれたというエピソードです。
「演奏会で停電になったんです。どうなるか、ひやひや。でも、演奏はそのまま。これって、指揮者は要らないっていうこと? 電気がつくと、父はいつも通り指揮棒を振り続け、演奏者もみんな楽器を奏でていました」
どんなときでも揺るぐことのない、患者と医師の信頼関係。医療分野に指揮者役の輪を広げよう!。先生はそのとき、そう心に誓ったそうです。
常にそばにいて医療を支援 顧問弁護士的な主侍医の役
一般に治療を担当する医師を「主治医」と呼びますが、これに対し医療判断医・寺下先生の場合は 「主侍医」、すなわちプライベートドクター。先生が考えられた造語ですが、健康なときから常に患者の傍らにいてサポートするという意味なのだそうです。
寺下先生は13年前から自由診療を全面的に取り入れ、健康なときから何でも相談できるこの、主侍医制度に取り組んでおられます。
慶応大学医学部でも「医療判断学」というテーマで講義をもち、それも7年になります。
「あなた方はがんの専門医。担当する40代の患者は、余命1年以内の末期がん。強力な抗がん剤Aが開発され、がんを80%完治させます。しかし副作用も強烈で5%は1時間以内に死亡。残りは変化なし。ほかに治療法がないとしたら、Aを使いますか?」
というように学生に仮想体験をしてもらうと、同じ6年間、医学を学んだ学生たちでも、まちまちの判断をするそうです。さらに患者が親だったなら、患者が自分だったなら‥と質問を変えていくと、その判断もさらに異なったものになっていくということです。
「6年間医学を学んでも、長年医師の経験を積んでも、この判断の不確実さは常に医療につきまとってきます」
だからこそ、「医療判断学」という学問を早期に確立させ、日本の医療の未来にささやかながらも意味深い頁献ができればとも考えているのだそうです。
主侍医とは、分かりやすく言えば「顧問弁護士のような存在」だと寺下先生。まだまだ実験的な側面もある活動だそうですが、「主侍医の役割を顧問弁護士のような契約で」というスローガンもロコミで広がって、契約は50以上にもなっています。
主侍医は単に治療や処置を施す医者という存在ではありません。普段から自分の健康に対する不安を相談し、いざ病気になった際には適切な医療をアドバイスしてくれ、必要なら優秀な専門医への橋渡しを行ってくれるのが主侍医だと寺下先生はおっしゃられます。
患者と医師は信頼関係で個々に応じたテーラーメイド治療を実現
「最期の最後まで治療を続けよう」
「いや、もう苦しませずに逝かせてあげよう」
26年前のことだそうです。寺下先生は兄弟4人でこんな会話を交わしたそうです。
先生のお母さんが劇症肝炎を患い、可能な限りの手だてを尽くしても回復が難しい状況だったといいます。2人の兄は医師になって6年目と2年目。先生ご自身は医学部の6年生で、弟は医学部1年生でした。そのとき、先生と長男は「最後まで治療を続ける」という意見、次男と弟は「苦しませずに逝かせてあげよう」というお考えだったそうです。結局、最後まで徹底した治療を続けることになりましたが、無念にも数日後にお母さんは他界されてしまったのでした。
その後先生は医師となり、治療の現場で大きな決断を迫られる度に、当時のそのときの会話を思い出されるそうです。どちらの選択が正解だったのか、いま振り返っても結論はつかないといいます。
「医師といえども自分の家族の治療は難しい」とはよく語られる言葉ですが、医師の判断と家族としての判断は、ときとして異なる結果になることも多いからです。
最近、EBM(Evidence Based Medicine)という考えが普及してきました。これは科学的な根拠に基づいて医療を進める、確率論的な判断方法です。確かにこれも大切なことでしょうが、実際の治療の現場では、そうした判断を単純に下せないことも多くあると聞きます。
「どうしたら、プロとして最善の支援ができるのか、日々、模索を続けているんです」
EBMが世界的に広がり始めたのは、90年代後半からといわれています。手術なのか、薬による治療なのか。薬ならAが適切なのか、それともBか、あるいは東洋医学は‥。
患者の治療法を選ぶには、これまでは医師個人や医療チームに蓄積された経験やノウハウに頼ることが多かったようです。
EBMは、それが本当に最善の選択であるかどうかの客観的判断基準として、いくつもの医学論文を統計的に分析し、そこから信頼度を割り出したものを使ってみてはどうかという試みです。しかし、実際の現場では教科書的な理屈だけでは患者さんの望む最善の医療にはなり得ないところが医療判断の難しいところです。
そこで私達は、科学的根拠(EBM)の比重を6割として経済的な事情や仕事との兼ね合いといった“社会的背景” 2割、治療への不安や精神的負担等の“心理学的情況”2割、を配慮した医療判断学を提唱し、一人ひとりに応じたテーラーメイド治療の実現を試みています。
免疫療法で変革されるか・・・がん治療へのさらに多くの可能性
今日、アメリカなどでは東洋医学の見直しや民間医療の再認知の一環として、代替医療の研究に対しても国の医療機関が本腰を入れ始めています。日本でも、検査漬けや薬漬け医療への批判という形で、同様の現象が現れています。
例えば、がんの診断や治療に関して、がん検診の有用性や抗がん剤の是非など、いま日本ではさまざまな論議が巻き起こっています。
がんの治療には現在、化学療法、いわゆる抗がん剤や放射線治療、手術療法、免疫療法などがあります。そのなかの免疫療法が今日、最も注目されている治療法といえます。つまり、人間が本来持っている自己防衛機構を何らかの方法で賦活させ、がんを治療し、あるいは予防しようとする試みです。
厚生労働省が医薬品としてしたもののなかにも、例えばキノコ類から摘出した物質がいくつもありますし、そうした類の健康食品の免疫賦活作用についても様々な機関が研究しています。例えば、アガリクスなどのキノコ類の食効を期待して、自分自身も使用している医師も多いようです。しかしその実、家族や親友には勧めることができても、一般の患者には誤解を生む可能性があるので推奨はできない、といったところが大方の見解ではないでしょうか。
「しかし、効果があったという複数の報告を見るにいたり、何とかしてきちんとデータを取って、正確な情報を提供できるように、専門医のネットワークなども作りたい」
誰もが客観的情報を知るチャンスを与えられ、主治医または主侍医と相談して使用できるようになることが今後、法的にも実践的にも望まれることではないでしょうか。