(概説)
発熱は最も多くみられる症状の一つです。発熱で来院される患者さんのほとんどは、何らかの感染症が多くを占め、次に膠原病を代表とする非感染性炎症疾患、内分泌疾患などが続きます。それらの診断がつかない場合に、いわゆる除外診断として本症を疑い、ストレス状況などの問診を深めることになります。一線の診療現場では、感染症や膠原病などの症状や検査結果の異常もなく、また、解熱剤の効果もない発熱が続く患者さんを診ることは少なくありません。その発熱のメカニズムは特定できませんが、体温中枢のセットポイントが一時的にずれたり、自律神経の失調によるものなどが推定されています。昔から「知恵熱」と言われているのも本症の一つでしょうが、それこそ先人の知恵でしょうか?
(症状)
多くは37℃台程度の微熱のみがみられることが多いですが、時には38℃を超える高熱が出ることもあります。熱以外の症状は乏しいことがむしろ特徴で、全身状態も良好なことが多いです。詳しい問診をすると、環境の変化や、生活上のストレス要因が疑われることが本症のポイントとなります。
(診断)
概説で述べたように、感染症やそのほかの炎症性疾患や甲状腺機能亢進症などを除外することにより、本症を疑います。血液検査でも炎症反応がなく、解熱剤が効かないことも診断の目安になります。生活上のストレス要因などの詳細を聴取することも大切です。時に薬剤性の発熱もありうるので、服薬内容のチェックも重要です。
(治療、対策)
発熱以外の症状がなく、上記の除外診断がなされたら、過度の心配をせず、1、2ヶ月やそれ以上の長期的観察をしましょう。その間に、ほかの症状が出現し、診断がつく場合もありますので、内科などで経過観察の診療を受けましょう。半年、1年後に気がついたら平熱に戻っていたということもよくあります。体温は個人差もあり、1日に1℃くらいの変動はありますので、日頃から自分の体温状況も把握しておくことが基本的な心がけと言えましょう。
作成:2024/05/23
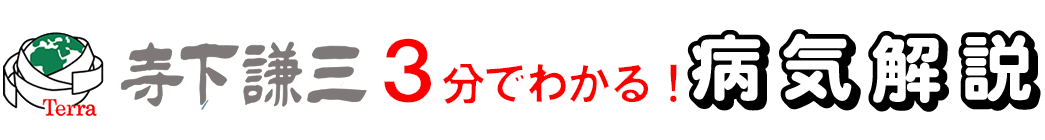
 心因性発熱
心因性発熱