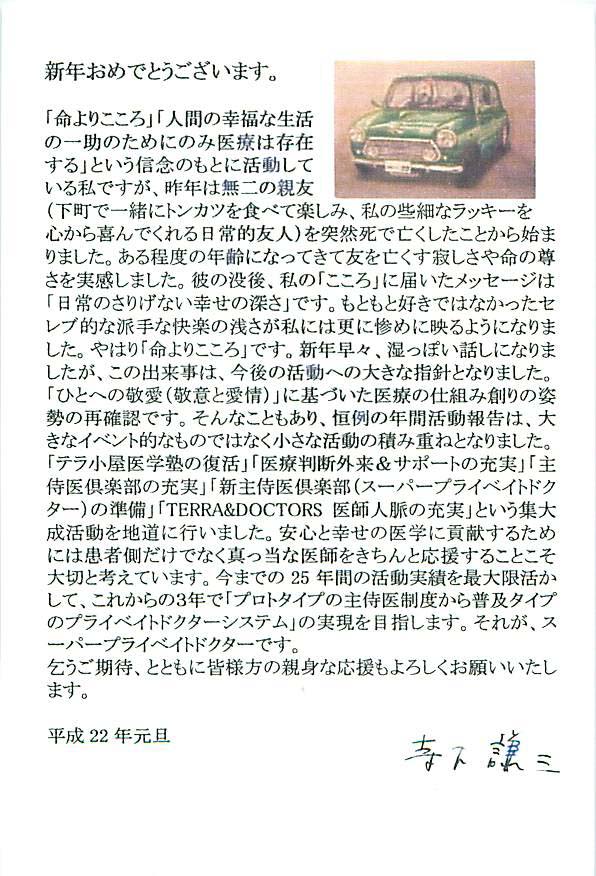ちょっと一言
◀︎前の20件 1 2 3 4 5 6 7 次の20件▶︎東北関東大震災に教えられたこと8「民主自民公明共産党結党の勧め」2011/3
2011年03月18日前項に続いて、復興10年は、超党体勢で日本を再建していくというくらいの思い切ったことが必要ではないでしょうか。この気の遠くなるような再建活動では、各政党のそれぞれの強いところが全て必要です。今やピュアな「共産主義」のシステムは成り立たないことは世界的な共通見解かもしれませんが、復興においては一部には共産的考えも必要でしょう。富のあまりにも大きな偏りはこれからの成熟した国には向きません。全てが均一では労働意欲がわかないから、頑張ればどれだけでも稼げるという仕組みは絶対必要だと人は言います。僕はそう思いません。「行き過ぎ」は必ず破綻します。極端な話、せいぜい平均個人所得の10倍が限度で、それ以上は99%が税金でもいいのではないでしょうか。「それでは産業は活発化しない」と多くの人に反発されます。息子の一人までから反論されました。「そこを工夫するのが、成熟型資本主義」ではないかと思っています。年間5000万円以上個人的に稼ぎたい方は一体何が欲しいのでしょうか?「命よりこころ」論(ここでは詳細を省きますので、ブログの他の部分をご参照下さい)と同じく「お金より栄誉」論も成立するかもしれません。社会としてのなんらかの工夫で、適切な成熟型資本主義のモデルを作るよい機会かもしれません。
話しは、飛びましたが、昭和の「戦争復興とその後の成長、競争社会」から平成の「欲望の権化化と安穏の入り交じりによる二極化加速と破綻」となり、これから「再復興」の試練が訪れました。やはりキーワードは「競争」から「協力」でしょう。今回の災害では、被災者またはその恐れがある人々と全く難を逃れた人々との決定的な二極化、全て失った人々や身動き取れない人々と余裕のある人々との二極化など、いろいろなところで二極化の権化が発生しました。それを利用して更に強者となるものを許すのか、本当の勝者は人の心にあるという流れが勝者となるのか偏見を持ちつつ見守りたいと思っています。小さな存在の僕ですが、前者は絶対に許さないという毅然とした行動をとりたいと決意しています。
東北関東大震災に教えられたこと7 災害時の報道のあり方への提言
2011年03月18日なんとこの1週間は長いことでしょうか?テレビは毎日悲惨な状況の報道ばかりで相当タフな人々も精神が参っていることでしょう。それでも、現地の被災者の方々、一線で救助や復旧に当たられている方々のことを思えば、そんなことは言っていられません。
そんな報道を1週間見続け、いくつか感じたことを書いてみます。
緊急分担報道体制の可能性は?
地震直後から、ものの見事に各チャンネルで被害の模様をリアルタイムに映像で報道を始めました。そのリアルタイム性にも驚きました。各チャンネル共にいつのまにかCMのない特別報道番組となっていました。この素早い対応には今から振り返ると驚嘆の一言につきます。この素早さが、政府や東電にもあればと思いましたが、テレビを見続けていますと、各放送局がそれぞれ強烈な被害の生々しい画像を繰り返し流します。どこのチャンネルも同じ内容です。安否確認や、救援活動の進捗具合や、インフラの状況や、連絡体制の問題や後には原発の状況や各人にとって知りたい情報は違うのに、とにかく津波の酷い被害状況を何度も見せられてしまいます。むしろそんな画像は見たくなくて、避難場所状況や安否状況や救援活動状況だけ見たい人もたくさんいたはずです。こういう時こそ、各放送局は協力体勢を敷いて、報道分担をするべきではないでしょうか?実際被害状況を映そうとする報道ヘリが邪魔になったようなことを、官房長官は話されていました。普段の報道ではスクープ合戦が大切なこともある程度は理解できますが、未曾有の災害と自ら報道しているのですから、未曾有の放送局分担報道をされたらいかがなものでしょうか?あるチャンネルは被害状況専門でもいいでしょう。あるチャンネルは、原発だけで、専門家も1放送局に一同に集めると、より正確な報道に努めるだけに留まらず、実際の復旧活動にアドバイスできることも可能かもしれません。また他のチャンネルでは、安否情報、避難所情報、インフラ情報、ボランティア情報など被災者に直接的役立つ報道を専門にします。被災者は、津波の映像を何度も繰り返してみたくはないのではないかと想像します。我々のように難を逃れたものにとっても、胸が痛む映像ですから。
ついでに政府の指導体制についても分担体制もあるのではないでしょうか?
地震の直前まで、民主と自民公明は醜い(?)争いの渦中でした。さすがに、被害の重大さのもとではそういった争いは引っ込みました。国会の休会問題では小競り合いがありましたが。そして、管総理のもとに、政府として民主党中心に総司令部が設けられましたが、ご存知のように、この広範で甚大な被害に対しては力不足の感は否めず、国民の不安は募りました。ここでも未曾有の災害が起こったのですから、未曾有の体制による対応もよいのではないかと思います。福島原発問題の指揮系統は自民党に任せる、被災者の保護やケアは共産党に任せる、自衛隊等による救援活動は公明党に任せ、民主党は全体指揮と復興活動の計画指揮などとして、各党首はそれなりリーダーですから、分担の決定権を持ち、党首同士が徹底的に連携するというようなプランはいかがでしょうか?
民主党だけではいかにも荷が重すぎます。東北関東大震災に教えられたこと6 文明に溺れた反省 2011/3
2011年03月18日多くの心ある日本人、知恵ある日本人が、感じたり、気付いたり、実際に発言提言したりしていたこと。
こんなに恵まれた生活をしていていいのだろうか?
こんなにいつでもどこでも食べたいものを自由に食べていていいのか
こんなに当たり前のように高層ビルばかり建てていていいのか?
朝から晩まで携帯電話やインターネットにしがみついていていいのか?
24時間開いているコンビニが当たり前としていていいのか?
深夜でもこんなに明るい町でいいのか?
頻繁に「自分にご褒美」でいいのか?
なんでも経済(お金)優先でいいのか?
バラエティ番組優先のテレビに振り回されてばかりでいいのか?
お風呂を2日も我慢できない人間であってもよいのか?
大体において「電気」の存在すら感じない電気依存症でいいのか?
なんでも自分中心、他人とは表面的な「携帯クリック」的お付き合いでいいのか?
書き出すときりがないですね。平成の日本人は、老いも若きも人情の面白味が激減したと感じている人は多いでしょう。僕も含め、そう思う自分のこともそういった傾向にあると感じつつ。
「行き着くところまで行って、崩壊して、また立ち直る」という自然の摂理に委ねるしか、人間の心の復興はないと神は考えられたのでしょうか?
それにしても厳しい試練です。
最近は、反省し始めた日本人も増えてきていたのではないでしょうか?
東北の地方の我慢強い対応をみていると頭が下がります。もし、これが東京に起きていたら、我々東京人は彼らのように粛々と耐えられるでしょうか?
東北関東大震災に教えられたこと5 勇気付けられる海外からの支援
2011年03月16日被害ばかりを報道して、救援活動が報道されない、と悲壮に思っていたら、海外からの救援隊の到着風景が報道されるようになりました。なんと心強いことでしょうか?実際には、言葉の問題も含め、指示系統をどうするかなどの難問があるとはいえ、「心強いイメージ」は大きいものです。また、各国首脳の「出来るだけの救援をしたい」というコメントも、いつもは日本から発していることが多いのだが、受ける側になると「有り難いものだ」と涙ぐんでしまいました。各国の新聞報道も日本への悼みの思いと復興への願いが伝わり、これも有り難く感謝の気持ちで一杯になりました。インドの中学か高校生たちが教室を暗くしてロウソクの火を灯しながら「Japan We Are With You」「Japan We Share Your Grief」と書いた紙を手に持ちながらお祈りをしてくれている写真には、目が涙で曇って見づらくなりました。心汚れていく人々も多い中で、今回の悲劇から、多くの人々の心の中に「本来の慈愛に満ちた人間のこころ」も復興するのではと期待しています。
僕個人にしましても、被災者の家族になるという希有な体験をし、その家族の消息が分かった時は膝をおり、声を被災後初めて聞けた時は、喉が詰まって声が出ませんでした。親族、友人から心配の連絡を頂き、気にかけて頂いていることに嬉しく心強く思いました。逆に心細い一人住まいの姪や帰宅難民にはお泊まりいただき、まもなく被災地から戻る息子とその友人を預かることになります。東京もいつ被災地になるかもしれません。勇気付けたり、人のお役に立とうとする立場でいられる今の自分の運命に感謝し、小さなことでも役立つと思うことを着実にしたいと思っています。十分水も飲めて、美味しいものを頂けるのを申し訳なくも思いますが、感謝しながらそれを楽しませて頂くこともできることの一つだと思います。「今日よりよい明日はない」という本を最近読みました。幸い災害から逃れた人が、粗食でもご馳走でも、ワインでも水でも、小説でもゴルフでも、感謝しながら楽しむことはいいのではないでしょうか。明日は出来なくなるかもしれません。決して刹那的な意味ではなく「今日よりよい明日はない」という平静の自分をじっくり味わい楽しむというスピリッツだと思います。
でも、被災者のために出来ること、今は節電や節電波(不要な携帯電話使用等)が最も大切なようですので、出来るだけの協力をしたいものです。今日の東京は暖かいですが、少しくらい寒くてもいいではありませんか、部屋の中にいれるだけで幸せですし、便座が冷たいくらい平気ではありませんか?ドライヤーも自然乾燥か3日や4日に一回の洗髪でもいいでしょう。また、富裕層といわれる方々には思い切った寄付もお願いしたいと思います。義援金と呼ばれる我々庶民からの小額の寄付を集めることも大切でしょうが、大口の寄付は手続きも簡単で効果は絶大だと思います。
アメリカで難を逃れた石川遼君。昨年の稼ぎの残りを全部寄付してはどうでしょうか?本当の国民的英雄になれます。そして、綺麗ごとを言ってはいるものの、国民大衆からお金をトローリングして、その力で政治家になろうとしているような偽善者のなかに潜む本当の人情を引き出す模範となってみてはどうでしょうか?
東北関東大震災に教えられたこと4 原子力発電保安員の記者会見から
2011年03月16日震災2日目の朝の保安院の記者会見に立った代表の説明にはいささか驚いたのは僕だけではなかったようです。さすがのテレビ局も途中でその中継を切り、アナウンサーの小宮悦子氏は「災害直後のこの場面で、この内容はいかがなものでしょうか」というまことに適切なコメントをされました。「言い訳」「保身」のための前置き的内容で固められ、中身がまるでない内容が延々と続くのである。この人の個人的な資質の問題もあるのでしょうが、いかにも役所的な無難な回答をする癖が身に付いているのか、上司から言ってはならないことをたくさん授かり頭が混乱していたのでしょうか。さすがに、次回からの記者会見に姿を現さなかったようです。僕は、最近の「何かと人の粗を探し文句をつける風潮(その最たるものが国会議員同士での小競り合いだった)」に、ほとほと嫌気がさしていました。マスコミもこぞってその風潮を鼓舞するから、どの業界も「まあ思い切った決断はせずに、ひとの流れに身を任せて、なにかあればその時の先導者に文句を言えばいい」という「事なかれ主義」が蔓延していました。その延長があの保安員の態度に現れていたのでしょう。「最悪の場合を想定した行動」は、最悪の場合が起こらなければ、「あんな余分なこと、あんな無駄なこと」をしなければ良かったのにと非難されることになります。「結果で決断の良し悪しを判断する」ことが当たり前になっているからだと思います。僕の仕事の「医療決断支援」でも同じことです。数多くの経験から、「どちらを選んでも幸せと思えるようになるまで、じっくり話し合って、内容を検討してから決断の助言に入ることが大切」と思い至りましたが、今回のような緊急の事態では時間がないのでその手法が成立しません。「どんなに恨まれても最悪の状態を阻止する」という気概がリーダーには必要なのでしょう。昔の武士は、それで結果が悪かったら、「腹を切って」いたわけだから、マスコミに叩かれそのため次回の選挙に落選するなら、それはそれでいいと「腹をくくって」はいかがなものでしょうか。
東北関東大震災に教えられたこと3 目立たない現場大衆の底力
2011年03月16日更なる被害の拡大に対する懸念のなか、今後の復旧がたいへん憂慮されます。しかし、これだけの被害の中、止まっていた電気が少しずつではありますが、復旧していることに驚いています。昨夜、仙台の息子と携帯電話で肉声を聞くことができましたが、その話しの最中に「あっ、隣の家の電気が点いた。あっこちらも、、、、!!」と早くも電気が復旧していくリアルな臨場感を感じました。息子は運良く、復旧が早い仙台の駅近くの友人のお父様が務める教会に非難させて頂いていました。それにしてもこれだけの被災の中を誰かが工事をして復旧させているわけですから、現場で働く多くの人の懸命な力のお陰なのです。オバマ大統領が就任挨拶で言っていた「アメリカの発展は、いわゆるセレブと呼ばれるような目立った人たちでなく、多くの目立たずこつこつと汗水流して働いてきた人々により作られた」という話を思い出しました。途方もないこれからの復活活動ですが、ほとんど忘れ去られようとしている昭和の戦後の復興の時のように、どん底からも明るく立ち直ってほしいものです。平成に生きる人たちの目に生き生きとした輝きが消えかけていたなか、夥しい犠牲者の方々に恥じないように、人を思い遣り、人のためなら粉骨精神で、滅私奉公という言葉まで生んだ誇り高い日本人の心も復興しなければならないと自分自身を戒めています。これは決して自虐的ではなく、自己の本当の喜びを探そうという意味です。孔子の教えだったと思いますが「どうすれば良いかを知ることは大切だ」「しかし、それを好きなことはもっと大切だ」「しかし、それを楽しむものには及ばない」という話しを思い出しました。多くの方の「命」を賭して教えて頂いた「命よりこころ」の真髄のような気がします。
東北関東大震災に教えられたこと2 リーダーの大切さ
2011年03月14日人は困難に遭遇したとき指導者を求めます。多くの人は、どうしていいのか当惑します。困難のまっただ中の人は、「どのようにして逃れたらいいのか」と迷い行動ができません。また、被害者を救済したいと思う人も「どのようにして助けたらいいのか」迷い、行動が遅れます。今回の巨大地震で、テレビのニュースを見ていた多くの人々はまず日本のトップがなかなか姿を現さないことに不安を感じていたのではないでしょうか。地震が起こる以前から、日本人は指導者を求めていました。最近は、マスコミが助長していることもあり、全ての分野において「上手くいかなかった時のクレーム」が激しいと感じています。日本のリーダたる国会議員もそれを恐れて思い切った行動ができません。しかし、この前例がない非常事態ですから、トップが思い切った対策を実行していくことが大切ですし、国民はそれに従い、マスコミは枝葉末節の不具合を責め立てず、大きな流れを大切にしていくという姿勢が大切だと思います。昨日、ようやく総理が「国民みなで力を合わせて乗り切りましょう」というメッセージを自ら伝えました。僕には、遅すぎると感じました。それでも、総理としては、国民の心を引っ張るメッセージでよかったと思っています。それにしても、取材の記者から、枝野官房長官に「どうして総理自ら具体的な質問に答えないのか?」というこの事態においてもマスコミの情けなさを露呈するようなあら探し文句をつけました。このような時はトップは「国民の士気を高めること」が最重要であり、各論はそれぞれの専門家に任せながら進むのがいいに決まっています。勿論、枝野氏は「それぞれの専門の担当者が質問には対応していく」旨を伝えましたが。それにしても、昨日13日午前に登場した原子力安全・保安院の「自己保身、言い訳だらけ」の答弁にはあきれかえりましたが、なにか決断して結果が上手くいかなかった時のことを考えすぎる役人、政治家が多すぎることの現れでしょう。僕たち医療の分野でもそうなりつつあることを反省しなければなりません。そのためには、国民の我々やマスコミの方々も大きく反省し協力しなければなりません。今回は、とても辛い試練ですが、「計画停電でも、節水でも何でも協力する。被災者のために少しでも役に立ち大局的に日本を建ち直していくためには」と思っています。勿論、リーダー任せではなく、国民のみなが出来ることから協力して、そして、たまたま被災からまぬがれた人は、暗くなりすぎず、明るく元気に力を貸し、また、有り難く毎日を過ごすことも大切だと思っています。
頑張り抜きましょう。囲碁王座の故藤沢秀行の「強烈な努力」という言葉が思い起こされます。
東北関東大震災に教えられたこと1 相互の思いやり
2011年03月14日震災の翌日、前日より泊り込みのスタッフと手分けして、僕のメインの職務である「主侍医」のクライアントメンバーに安否確認の連絡をしました。幸い、ほぼ全員の方と連絡が取れ、大きな怪我などがないことが確認されました。その連絡活動の際に思ったことは、ほぼ全員から「先生方は大丈夫ですか?」という逆にこちらの安否を気遣うお声をいただいたことです。「患者も医者も笑顔になれる医療システム」を掲げる僕たちにとって、この上もない喜びの言葉です。日頃、このような方々の健康を守ることを職務としている有り難さに、スタッフ共々身が引き締まりました。医師と患者、親と子供、政治家と国民、車と歩行者、お金を貸す人借りる人、被災者と救済者、どちらにも上下や強弱があるように見えますが、「人間同士」であることに違いはありません。そういうものを超えた思いやりが人を動かすのだなあと実感しました。
東北関東大地震、被災の方々にお見舞いとお悔やみを申し上げると共に、直接救済に当たる方々に感謝し、その他の方々の暖かい支援に感動しています。
2011年03月14日突然の出来事がまだ夢の中にいるようです。3月11日午後2時45分ごろ、事務所で妻とPC画面に見入っていました。この3月に還暦を迎える友人のサプライズパーティを企画するための情報集めのためです。なんと平和な情景だったことでしょうか。金曜日の3時前であり、事務所の電話もならず、このまま平和な一日、一週間が終わるのかな、という気持ちも芽生えた頃合です。僕の事務所は、契約者の方が、健康上の困ったことや一大事の時に連絡があるから、電話が無いということは平穏無事なよいことなのです。最初は、妻が体を揺すっているのかとも思っていたのが、めまいではないかという思いにかわり、これは地震だと思うまでの数秒がまるで数分以上あったように思い出します。いよいよ揺れが強くなり隣室の事務室へ行き、スタッフ3名と立ったまま呆然としていました。全くといってよいほど、呆然とする以外にするべきことが浮かばないのです。「心配していた関東大震災がついにきた」と覚悟しました。10秒程度でかなりの覚悟をしてしまうのだから、人間の対応力にも自ら驚きました。スタッフの一人が、インターネットで調べて「宮城が震源地らしい」と叫ぶ。「仙台にいる息子は大丈夫か?」頭をよぎりました。少し揺れが落ち着いたところで、テレビをつけてニュースをみる。数分後には「大津波が襲う。東北地方は厳戒態勢を」との報道。東京の揺れのすごさにも驚くが、震源地が宮城の方であり、津波もあると聞くと「一体どうなるのか。息子は大丈夫か?」あっという間にテレビの映像で、凄まじい津波の様子がリアルに映される。夢の中の地獄のようで、現実感がない。すぐに息子の携帯へ電話するも、つながらない。メールも同じ。これは覚悟しなければならない。妻にどのように伝えるか。それを考えただけでも、辛い、辛すぎる。ほんの数分前まで、平和に過ごしていたのに。
東京より北の被災地の人々は、おおよそ同じような状況であったでしょう。大きな被害を逃れた人々は、このようにこの2日間をずいぶん昔のように思い出していることでしょう。大きな被害に会われた方々は、現在もなお被害が進行中で、思い出すというどころではないでしょう。
被災地にいる息子とも昨夜10時にようやく電話で連絡がとれ声を聞くことができました。他の被害者がたくさんいるのに不謹慎ですが、安堵の気持ちで声がつまりました。僕も知っている友人のご実家にお世話になっているとのことでした。お父さんは牧師さんで、その教会の近くだそうです。「神様に助けていただいたのだから、今度は被災のみなさんに出来るだけのことはしなさい。そしてこれからの人生もこのことを忘れず、人のために尽くしなさい」妻が息子に伝えました。
同様の体験をし、深い悲しみに泣き崩れている方、安堵の涙を出されている方、何かしてあげたいが何も出来ないと地団駄踏んでいる方などいらっしゃるでしょう。僕も、最初は父親として息子にしてやれる最大のことは何か、と考えました。息子の消息が判明し、次は息子の周囲にいる人たちへ何が出来るか、と考えました。テレビの報道をみるにつけ、その次は何が出来るかと考えました。まるで何も出来ない自分がはがゆい。
この大地震を通じて、わずかな間ですが、いろいろなことを教えられました。そのことをみなさんに発信することは出来る。僕の本来の仕事を着実に続けながら、せめてそんなことを通じて、お役に立ちたいと思いました。みなさん方も、各人が少しでもできることからしていきましょう。それが大きな力になっていきます。
「東北関東大震災に教えられたこと」を思いつくまま、興奮が冷めやらないうちに書下ろし、ホームページに載せていきたいと思います。
これは僕の本来の仕事「医療決断の支援」の精神にもつながるものと思っています。
(内容に鑑みて、僕の本来の文体ではなく、です、ます調にて書かせて頂きますことをご了解下さい)
「患者も医師も笑顔になれる仕組み作り」
2011年01月31日嬉しかったクライアントメンバーからの報告
僕の実践している「主侍医システム」の目指すところを一言で言えば「医師も患者も笑顔になれる仕組み」である。勿論、患者の家族や医師以外の医療スタッフも含んでいることは言うまでもない。
ところが現状はどうであろうか?
「この医者は信頼できるのだろうか?真剣に取り組んでくれているのであろうか?」「医療ミスは大丈夫だろうか?」「もっといい治療法はないだろうか?」など不安が次から次へとよぎる。また、インターネットやテレビからの情報を見ると不安は更に増大する一方である。病気で心細いのに、更に迷いや疑いがあると笑顔どころでなく引きつった表情となってしまう。
「この患者は本当に信頼してくれているだろうか?」「きっと誰かにセカンドオピニオンと思っているだろう」「テープレコーダーを潜めているかもなあ」「訴えるようなことはするタイプではないだろうか?」
引きつった表情を見ているとその思いは更に強くなる。笑顔で接しようと思っても「私が苦しんでいるのに、笑うのですか、とも思われかねないし、、」と医師も引きつった顔となる。
大げさな空想のような話しに思えるだろうが、結構事実に近い。医療崩壊の根底に流れる要因の一つだと僕は思っている。
そんな中、僕の主侍医クライアントのメンバーから嬉しいお礼の連絡が入った。ある病気の診療のために、母校東大病院の専門医の受診をして頂いた。最初の診察に僕も同伴することになった。初めてお願いするドクターだから、顔を合わせてご挨拶もしておこうと思ったからである。准教授にあたる中堅の医師Aドクターが担当となった。初診ということもあったのか、1時間近く時間をかけて、診察説明をしてくれた。後半の説明の時には、僕も診察室の中でご一緒した。Aドクターは、「先輩まで来て頂いて恐縮です」と懇切に説明してくれた。
帰りがけ、そのクライアントに「大学の医師で、あれくらいに丁寧に対応してくれるのは珍しいね。しかもアドバイスも的確で信頼できる」ということを具体的に説明した。また、そのAドクターにも、後日お礼の連絡をした。勿論、医学的内容のやり取りも行い、今後の治療方針についても検討した。彼は「先輩までご一緒に来て頂いて感激しました」と言ってくれた。僕は彼に「Aさんのようにキチンと対応できる後輩がいて心強い」ということを伝えた。
その1ヶ月後の再診を終えた後、そのメンバーから連絡を頂いたのである。「最初は、実のところ大学の先生で怖い感じもして緊張しましたが、今度は全然違いました。寺下さんから、お話を聞いていたお陰で今度はリラックスして、信頼してA先生とお会いできました。すごく親切で、的確なアドバイスを懇切丁寧にしてくれるし、冗談も出るし、正直感動ものでした。これからは、少し遠いですが東大病院に通うのが楽しみになりました。」
これは、メンバーの方やAドクターが別人に変貌した訳ではなく、人間性や優秀性や取り組み方に変化はない。少し潤滑剤が入っただけのことである。こうなると良循環である。自然と理想的な患者医師関係が築かれていく。
まさに「患者も医師も笑顔になった」と主侍医の僕も笑顔になれた訳である。
医療の各論的技術の発展も大切だが、その発達した医療技術をどのように提供していくかのシステムこそ、「幸せに貢献する医療」に不可欠である。ソフトバンクの孫さんが「デジタル情報テクノロジー」の時代から「デジタル情報サービス」の時代に突入しつつあると言っているが、医療の分野でも同じである。「ヒューマンメディカルテクノロジー」から「ヒューマンメディカルサービス」の時代となるであろうと考えている。せっかくのテクノロジーをどのように提供するか(How to serve)に知恵を集めていかなければ幸せに貢献する医療は実現できない。再生医療や遺伝子医療の研究も大切であろうが、医療の仕組み作りの分野にも更に優秀な医療人材が必要とされている。
アップルのジョブズ健康問題による療養報道に揺れた株式市場
2011年01月28日数日前に、このタイトルのような報道が一斉にニュースになった。アップルは今や世界を代表するような巨大企業である。そんな大企業のトップとはいえ、一人の人間の健康不安がその会社の株価を暴落させ、市場全体の急落も懸念されたというニュースに「やはり企業にとってもリーダーが命なのだ」と再認識した。僕の仕事は「主侍医システム」の普及だが、その柱として「主侍医倶楽部」と呼ぶ民間版侍医サービスの研究開発型実践を行なっている。クライアントメンバーの方々は、企業や団体、業界のトップの方が多い。その人がいなくてはその組織が成り立たないような方々ばかりである。
そんな主侍医倶楽部であるが、運営開始当初の20年前には、その会費が会社の経費にならないということで、よく問題になった。その頃はバブルの頃で、過剰な接待がまかり通り、いろいろな企業がゴルフ会員権を買いあさり、タクシー出勤は当たり前、取締役はハイヤー付きといったご時世であった。にもかかわらず、企業のトップの健康管理を経費として認めなかった(今も厳密にはそうかもしれないが)のは、税務当局(その他の日本の国の仕組みもそうだが)の型にはまった思慮の浅い見解だ。勿論、企業や団体にとって、そのトップが今の政治のように、誰がなっても代わり映えしないのであれば、確かに経費の無駄かもしれない。いずれにしろ、その企業のトップの健康管理に関する費用が経費となりうるかどうかは、税務当局が決めるのでなく、株主が(役員会であったり、社員であってもいいが)決めることではないだろうか。株主が、「この人がいなくなれば、先行きの業績が心配だ」と思えば、その人の健康が何よりも最大の資本となるわけで、企業にとってそれを守るために最大の努力をするのが当然であり義務ともいえる。
「健康管理の費用も含んだ」報酬を会社は代表に払っている、との反論があろうが、日本の場合は、それは実態に合わない。残念ながら、社長という重責にありながら(あるがゆえにと本人は思っているのであろうが)、なかなか健康管理には時間もお金も割かない傾向が日本にはあるからだ。特に日本の会社人間は経費は平気で使うのに、ポケットマネーとなると使うのが苦手になる。しからば会社として、会社を守るためにもトップの健康管理を義務づけるような仕組みが大切ではないかと思っている。
アップルのジョブズは、さすがに最高の医療を受けてきたから、大病を乗り越えて今日までやってきたのだろう。そのお陰で、我々はIpad、Iphoneなどの恩恵に浸ることが出来ている。
皇族だけでなく、「侍医」を持つという「未来の当たり前」をまずは自他ともに「キーパーソン」と認める方々に実行して頂きたいと、(若干宣伝にはなるが)心から願っている。
提供側にもユーザー側にも先駆者がいてこそ、大衆が恩恵を受けるシステムが育っていくものだと僕は考えている。
主侍医倶楽部営業部 2010/9主侍医通信より
2010年10月07日
驚異的な暑さが続く夏でしたが、みなさま体調はいかがでしょうか?現在のところ、主侍医契約を頂いているメンバーの方々には大きなトラブルもなく無事通過できたのではと安心している次第です。
まだまだ気候が不安定ですので、くれぐれもご用心を頂きたく思っております。暑さが長かった割には、快適な秋が短く寒さが早く訪れるのではと心配しています。そうなると昨年流行したインフルエンザの再流行が懸念されます。今年のワクチンは新型、季節性が同時に行なえるようなものになっていますので、私どもでは、早めの対策をお勧めしています。
「主侍医倶楽部」を運営し始めてから20年が経過します。これだけ長年お付き合いさせていただいておりますので、癌や心筋梗塞等重大な病気を避けることはできませんが、全て早期発見にて早期対処が出来て、病気を持ちながらも全員がお元気に過ごされていることは、私どものこの上ない喜びです。これもみなさまには日頃から「健康は第一」と考えて頂いているお陰だと感謝しておる次第です。そうは言っても、私も含めて寄る年波には勝てません。私どもスタッフもメンバーのみなさまも高齢化が進んでいることは認めざるを得ず、今後、様々な難関が押し寄せてくることも覚悟せねばと気持ちを引き締めております。第一の対策として、私としては、医療判断医の後輩の育成と専門医とのコネクションの更なる充実(数だけでなく質と密着度においても)を念頭に置いております。スタッフとしてはなるべくみなさまと頻繁にご連絡をお取りすることを心掛けるようにしております。
良質なサービスを提供するには、あまり量の拡大はできないという自己矛盾を抱えております。「スモールメリット(メンバーのKさんのお言葉です)」を活かしながら、ある程度の量の確保も重大な課題と考えております。我々の活動を理解いただける方々への参加をお願いするにあたり、私が陣頭にたった主侍医倶楽部説明会を定期的に行ないたいと考えました。「契約者を拡大したい」という運営上常に存在する願いと「主侍医活動を理解して頂いた方のみにご案内したい」という我々の願いとの両立を実現するために、なるべく丁寧にご説明したと考えております。これを機会に、みなさまのご意見も参考に新たな契約形態の追加も検討しております。まことに我田引水でありますが、日本の医療の現状を考えると、契約制の主侍医を持つことは「奇跡的な安心」だと思っております。どうか大切なご友人の方にお声をおかけ下さい。
また、既にメンバーでいらっしゃるみなさまにも、我々をより有効にご活用いただけるような説明会でもありたいと考えておりますので、万障繰り合わせてご参加いただけると幸甚でございます。
ベビーマッサージの本できました!
2010年07月15日なんと、ベビーマッサージの本の監修をしました。7月20日発売です。
「赤ちゃんとの愛着を深める」普及活動をしている日本アタッチメント育児協会の廣島大三さんとの出会いと今回の出版社の保健同人社さんとの長い付き合いから生まれました。といっても担当の森さとこさんが偶然にも僕を発見してくれたのがきっかけです(ありがとうございます!)
ベビーマッサージは僕の仕事の基本テーマである「命よりこころ」とも関係します。先日「戦中・戦後子育て日記」のところでも書きましたが、親子の愛着関係が人間や動物の基本になると僕は考えています。最近では、この愛着が「執着」に変性しているのではと心配しています。実は、最新の子育て方法論としての「ベビーマッサージ」と「戦中の子育て」との共通点に気付きました。それは子供への愛着の深さとその鏡的反射による親側が享受する喜びです。時には「くるたのしい」という河合隼雄さんの造語にも近いところがあるでしょうが。この相互愛着関係は、親子のみならず、おばあちゃんとお孫さんはもとより、夫婦でも先生と生徒でも会社の上司と部下でも、友人の間でもあります。そういった触れ合いの原点が「ベビーマッサージ」のなかに込められています。本の最後の方に、少し僕の個人的な考えを書かせて頂きました。
ここでは、ベビーマッサージそのものではなく、その底流に流れる心の問題を、お話ししているので、男性の上司が女性の部下に、「ベビーマッサージ」を実際にやらないで下さいね。その場合は「セクハラ」の対象になります。
「執着」ではなく「愛着」を全ての愛すべき人に、と言っているだけですので。念のため。
今回は、自分の本の宣伝でもありますので、「デスマス調」でしたためてみました。
「お金に印」をつける。「美しい稼ぎ」と「美しい使い方」
2010年06月24日前回、役員報酬1億円以上開示の話しをした。「美しい稼ぎ」の予告をしたので、勢いに乗って、続いて書くことにした。よく「お金に印はついていないから、○○で結構です」というような話し方を聞く。経済価値と言う意味では、1万円は1万円である。為替変動も、そういった価値の平準化のために本来存在するから、まさに「お金にしるし」はないはずなのである。しかし、僕は、いつの頃からか「お金には色がついているなあ」と思うようになってきた。よい例が、倉本聰の「北の国から」で純君が貧しいお父さんから汚れた1万円札をもらったが、その「なけなし」の思いを、泥のついたお札に感じ、ずっと使えないで封筒に入れて大切にしていたあの場面だ。このドラマを観た人は、印象に残っているのではないだろうか。このドラマを見た人には「お金に印」の説明はいらないであろう。
1億円以上の年俸を開示するのはよいが、もっと推奨したいのは、その使い道を開示することだ。もし、生活が慎ましやかであるが、報酬の多くを福祉施設などに寄付したり、部下の慰労にせっせと身銭を切っていたりしているのなら、それこそ高額報酬を取るに相応しいあっぱれな方であろう。具体的には、今の日本では、家族の人数にもよるだろうが、せいぜい数千万円もあれば、贅沢な生活ができるだろう(僕には想像でしかないが)。それ以上は「死に金」になる恐れがある。悪いこと(なんでしょうか?)に使ったり、相続で子供たちがもめる材料になったり、働かない子供を造り上げたり、、、など。
ここで、恥をさらそう。僕が、医学事務所&クリニックを始めてから、26年にもなるのに、業績は低迷している。しかし、業務は滞りなく行い、多くの人の役に立ってきたと自負はしている。主侍医という「民間の侍医」を契約ベースで提供している。契約には、いくばくかの契約金と、月額10万円以上の費用がかかるから、普通の人にはなかなか手が届きにくい。そこが辛いところでもあるが、今のところ仕方がないので、別途奉仕的な相談業務も行うことで、自分を納得させている。そんな高品質ではあるが、若干高価でもある医療サービスを提供しているが、未だに年間の売り上げは低迷し1億円は遥か遠い目標となっている、恥ずかしながら代表である僕の報酬は、若手の勤務医程度である。税務署に睨まれるどころか笑われるはめになっている。やや贅沢なスペースであるが華美ではない事務所の家賃(ローン)を払い、僕を含め3名の主侍医と7、8名の救急担当主侍医と4名のスタッフの給料に振り分けているが、誰も貧乏にあえぐような生活ではないし、そこそこ誇りを捨てないでもいいくらいの生活は出来ている。営業や人材確保の先行投資や万一に備えてのリスクヘッジまでの余裕がないのは、経営者として失格気味なのだが。言いたいのは「1億円」とはそれくらいのお金なのだということだ。「一億円の報酬は、私のような優秀で選ばれた人物には当然」と思っているご仁もいるであろう。それを言うなら、僕の事務所、代表の僕は東大の医学部出身で、それなりの研修を積んで、経験も30年ある。一人のスタッフドクターは、東大の後輩であり、優秀な上に人格もよろしいし、勉強好きで現在東大の法科大学院で司法試験にもチャレンジ中である。もう一人は慶應の教え子であり、学生時代に「塾長賞」まで頂いた優秀で、これまた抜きん出た性格の良さである。救急を支えてくれる数名の医師たちも、教授や部長クラスを交えての陣容。事務局専任スタッフもみな、20年以上勤続の精鋭たち。手前味噌と言われるかもしれないが、これが束になっても「1億円役員」の能力に敵わないとはとても思えない。
再度言うが、「1億円」とはそんな額であるということだ。これを理解するためには「お金には印がついている」と思うしかないであろう。そんな報酬を頂くのは、決して会社から頂くのではなく、漢字がその逆の「社会」から頂くのだから、「生き金」として、世の中の模範となり還元するようなあっぱれな使い方をして欲しいものである。是非、「使い方」の開示を実現して欲しい。
つまり「ノブレス・オブリージュ」の考え方である。
これに関して、更に言及すれば、世の中には1億円などとは桁違いに稼ぐ人がいて、大衆も「あのゴルファーは、野球の選手は、1億円しか年俸がない」などと言うくらいに感覚が麻痺してきている。人間はほとんどの刺激に対して慣れ現象を起こすからだ。しかし、そういった超人的に稼ぐ人は、やはりその使い道に「ノブレス・オブリージュ」を意識して欲しいと願っている。
そのためにアイデアがある。年俸5000万円くらい以上から、福祉目的に税金が累進的にかかり、1億円以上は99%を税金とする。しかし、そのお金には印を付けよう。お札に「遼」とか「ビル」とか「マイケル」とか印刷し、福祉目的で使う。「遼に感謝しながら、介護を受ける」とか、「ビルのお陰で、老後が安心」となれば生き金となるだろうし、遼もビルも鼻が高いから、稼ぐこともまんざらではない。空想ではあるが、楽しく明るい空想ではないだろうか。
最近の報道で、この不景気なのに富裕層の人数が増えた、とあった。危険な徴候だ。「分かりやすくするためには、極端に考える」というのが僕のひとつの思考ルールであるが、もし、世の中の10%が超富裕層で、残り90%が報酬は最低限でもそれなりにゆったり人間らしく生きたいという層の2層になったらどうなるだろう。もはや超富裕層のお金の価値はなくなり、そのお金で買えるサービスは限定され(サービス提供者がいなくなるから)、富裕層間のチップのようになり果てはしないだろうか?まあ、この危惧は現実的でない、空想、妄想であればいいのだが。富裕層のみなさま、自分の首を絞めることの無きよう、欲張りすぎないように。
役員報酬1億円開示に思う
2010年06月24日最近の新聞紙上を賑わしているもののひとつに「役員報酬の開示」問題がある。1億円以上を開示すると最初に聞いた時に「そんな高額なのは滅多にないよ。その半分位から開示してもいいのではないだろうか」と思った。ところが、豈図らんや。続々と登場するではないか。驚きであきれかえってしまう。そしてまた、開示に反対する経済界の重鎮たちがいることを知り、不思議に思っている。アメリカなどと比べると、1億円くらいの年俸は低いと言っているご仁もいる。話しにならない。そういう人たちは「勤務医と開業医の報酬」論争の記事をどういった思いでみていたのだろうか?彼ら役員報酬開示の金額の大凡10分の1以下のレベルでの論争なのである。
僕は、報酬やら儲けには限度があるべきだと考えている。普通に質素に生活すれば、今時は、年俸300万円でも暮らせると言われている。かといって資本主義の現在、世の中の発展のためには「頑張って稼ごう」というような向上心が働くエネルギーとして必要なことくらいは理解している。そのためには、必要最低限年収に近い額の10倍かせいぜい20倍くらいまでの格差は容認しないといけないであろう。しかし、それ以上は、そもそも過剰なのである。一般的に過剰なものは還元せねばならぬものだ。さもなくば破綻がいずれ訪れる。お金を中心に(実際は、お金だけでと言ってもいいくらいだが)物事の価値判断をせざるを得ないアメリカ型経済価値観が世界中に蔓延している。スポーツ選手も芸術家も学者もただのお金持ちも同じセレブというくくりで集まる最近の風潮。面白味がなくなったと思っていたが、危険な徴候を示している。相撲界の事件がその例かもしれない。そして、我々も、情けないことに、音楽家でも画家でも(医者でも)有名であることや肩書きや所属先などだけで評価をしてしまう。勿論、実力があったからこそ有名になったのであるが、何事も行き過ぎはよくない。
話しを戻そう。役員報酬について。「会社の業績に見合った額である」「経営者の特殊な能力で会社は巨大な利益を上げたのだから当然」尤もな話しに見える。人間の能力の格差は歴然たるものがあって、一握りのリーダーが歴史を塗り替えてきたし、天才の発明により、我々は当たり前のように電気文明を享受し車にも乗っている。才能ある者は、世の中のためにつくすものだから、それはそれでいい。しかし、才能ある者が、弱者から搾取することとは随分違う。歴史を塗り替えるくらいの才能は希有なものだが、弱者から搾取するくらいの才能はたいしたことはない。極端な話しをしたが、こういったことを防止するためにも、大企業の役員報酬の制限をするべきだと僕は思っている。そもそも大企業は(マスコミも一緒だが)、それだけで巨大な力を持っていることを自ら認識すべきだからである。いくら優秀な人でも、個人の力ではなしえないことが、大企業の看板があるからできるのである。その大企業は、過去の多くの人の力の結集で大きくなったのである。業績に直結連動する報酬システムを取っているから当然そのようなやり方になってしまう。役員が数多くいる大会社には、大した働きをしないのに、毎日、会社のお金で飲み食いだけしているような人が結構いると聞く。大病院で、50歳を超え部長クラスになった今でも当直業務を週に1度以上やり、早朝から夜遅くまで勤務する優秀な医師たちの報酬の数倍をそんな人たちでさえ貰っているとしたら、搾取以外のなにものでもない。
医療界を理解して頂き、[医療崩壊]を食い止めたいために、この文章を書き始めた。高額役員報酬をもらっている人たちの言い分は、大きな声では言えないだろうが、「私の優秀な経営能力で稼ぎ出したのだから。報酬の格差は、人間の優劣があるのだから仕方ない」と思っているのであろう。では、優秀論について、俗っぽく考えてみたい。学生時代を振り返ったり、子供たちの受験について思い出してほしい。「いい大学に入りなさい。東大、京大を目指しなさい。国公立の医学部をなんとか。」僕たちが、ある程度大人になって迎える最初の登竜門が大学受験であることを否定する人はいないだろう。そして、国公立の医学部がいかに難関であるかは、ほとんどの人が知っている。勿論、大学受験ごときで人間の優劣は決められないが、ひとつの尺度であることは、誰しも認めているからこそ「学閥」なる言葉もあるし、高い授業料を払って有名予備校にいったり、有名受験校を目指す訳だ。そんな医学部OBは、一流企業の役員たちと、平均的に見て遜色のない優秀な一群である。その群間の平均年俸には数倍以上の開きがあることをどう考えるか。先ほど、例に挙げた50歳の大病院部長の平均的年俸は1000万円台くらいだ。また、どんなにのぼり詰めて、日本を代表する病院の院長になったり、大学の医学部長になっても3000万円を超えるとは思えない(実際、調べた訳ではないが)。勿論、魂か身体を売ってまで稼ぎまくると言われる医師もいるだろうが、たかが知れている。
では何故、受験戦争で勝ち抜いた彼らが、そんな低報酬(大企業の役員から見れば)の世界でいるのか?答えは簡単だ。お金以外の価値観で生きているからである。人のために尽くす喜びを知っているからだ。しかし、最近、医療紛争ブームを契機に、医師を敵視する傾向が高まり、善良な医師たちのマインドが急低下してきた。そうなると医師の価値観が揺らぐ。他の企業人のようにお金の価値観を優先するようになるかもしれない。すでに危険な徴候も出てきている。エステサロンのような「お客様は神様です」的クリニックが増えてきたし、東大の医学部を卒業して、外資系の証券会社に就職する人も出てきた。頭のいい人はさすがに先見の明があるのだなあ、と仲間内でも苦笑いだ。「医師という職業には、偏差値70を超えるような秀抜性はいらない。まずまずの頭脳とすぐれた器用さと盤石の体力を持ち、きちんとした使命感が根底にあることのほうが重要だ」というのが僕の持論である。ならば、東大の医学部など受験戦争の権化のような特殊なところでは、卒業しても他の分野に行くことは気にせず、むしろ医学部の過剰人気が低下し、医学部の受験が易しくなり、むしろその考えにとっても好都合では?とも反論される。部分的にはその通りだが、日本はとかく行き過ぎる傾向にあるから、ある程度以上優秀な人材が医学部で確保できなくなる時代がくるかも知れないと危惧している。
世界に誇る日本の医療水準を守るために、みなさまにより深い理解をしていただきたく、かなり過激な思想を書いた。
次の機会に、資本主義における「美しい稼ぎ」のあり方について意見を述べたい。
「戦中・戦後子育て日記」を読んで
2010年06月17日「はやぶさ」と事業仕分け
2010年06月15日東大卒業式に参列して
2010年03月26日感染症学術セミナーを開きました
2010年02月24日新年おめでとうございます
2010年01月04日