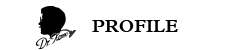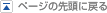あきらめない! 手を抜かない! やりすぎない!
 |
あきらめない! 手を抜かない! これが名医の条件 |
週刊女性 2006.2.21 主婦と生活社発行 |
自分の身体のことを安心して任せられる医師が、あなたにはいますか。
水と医療はただ同然と思われてきた日本の医療現場に、ここ数年、変化が起き始めている。従来の保険診療と一線を画し、医療者が診療料金を決める“自由診療”のクリニックが増えてきたのだ。当然、医療費は高めだが、医師がじっくりと患者の話に耳を傾
け、患者と話し合いながら医療方針を決めていくため、患者の満足度は高い。
東京・千代田区のJR飯田橋駅から歩いて5分の『寺下謙三クリニック』は、16年前、時代の先頭を切って自由診療をスタートさせた。
寺下謙三医師(52)がユニークなのは、“主侍医”という自ら信ずる理想の医療を実践してきたことにある。「大学病院に勤務する中で、医療にとっていちばん大事なことは、“安心”ではないかということに気づいたんです。考えてみれば、世の中でいちばん安心して医療を受けているのは天皇陛下ではないだろうか。健康なときからそばで診ている天皇陛下の『侍医』のシステムこそが、理想
の医療のあり方ではないかと思ったのです」
こう考えた寺下さんは、一般に使われている“主治医”を“主侍医”に変え、外来での診察と並行して『主侍医倶楽部』を設立した。ここでは患者はクライアント(依頼者)と呼ばれる。日ごろから医師と勉強会や趣味などの交流があり、一昨年より緊急時には携帯電話で24時間サポートが受けられる『緊急主侍医ホットライン』もスタート。「アメリカの弁護士さんみたいな感じで、身体のことは全
部お任せしています」
実はデザイナーのコシノジユンコさんも『主侍医倶楽部』の会員のひとり。たまたまディナーパーティーで隣の席にいたのが寺下さんで、コシノさんが長年ワインを飲むと日のまわりが赤く隠れる悩みを打ち明けた。すると、「それはアレルギーですね。眼科の専門医に僕が電話を入れてあげましょう」
それまでというもの、コシノさんは病院へ行くたびに眼科と皮膚科をたらい回しにされ、病院に対しては不信感を抱いていた。ところが、寺下さんが紹介してくれた眼科医は1回の診察で原因を特定し、長年の悩みをウソのように取り去ってくれたのだ。このときの診察眼の確かさと、絶妙な医師の連携プレーに感動して以来、コシノさんは“寺下ファン”となった。
「世界中どこにいても気楽に話を聞いてくれる医師がいるって最高です。さらに、“去年は乳ガンの検査をしましたから、今年は胃と腸をそろそろやりませんか”といった具合にキチンと健康管理してくださる先生がいる。これが私のいちばんの自慢ですね」
クリニックを訪れた人は最初、ためらう。3階建ての建物は病院というよりも個人宅。入り口には寺下医師の似顔絵と『寺下謙三クリニック』と書かれた小さなプレートがある以外、病院らしい表示はまったくない。
そして、待合室に1歩足を踏み入れた患者たちは、一様にこうつぶやく。「あ-、落ち着く・・・…」
アンティークの大きなテーブルの周りの壁には医学や健康関係の本がズラリと並び、ヨーロッパの個人の家の書斎に足を踏み入れたような錯覚に陥る。
診察室もしかりで落ち着いた木目の部屋にはアンティークのテーブルが置かれ、テーブルをはさんで医師と患者が
同じ目線で謡ができるように配慮されている。
「最初のころ、初診は1時間で十分と思っていたら、いつも2時間になってしまうんです。一般の外来では患者の講を聞くのは15分が限度ですが、話すことによって医師と患者の間に信頼感が生まれる。安心は、この信頼感から生まれるものですからね。僕は初診の問診というのは医師と患者の関係を創造する、とても貴重な時間と思っています。そして、患者さんから情報をたくさん得れば得るほど、医者としても判断がしやすくなり、その後の医療のレベルも上がるんです」
ちなみに寺下医師の初診の診察料は1時間で7万3500円、2時間で10万5000円。安いか高いかは別として、ここからが寺下医師のユニークな治療の始まりだ。問診を参考に、病状と患者の個性に最も合った医師を自作の『ドクター情報ファイル』から選び出す。そして寺下医師の指揮のもと、共同治療が始まる。
「22年前、腕のいい医者を集めようと思ったとき、いい医者の条件を、“あきらめない”“手を抜かない”“やりすぎない”の3つを基本の柱に決めました。なぜやりすぎがまずいかというと、やりすぎると人は傲慢になり、功名を求めて人の道を誤る可能性があるからなのです」
現在ファイルには1000名近い医師がノミネートされている。医師の名前の下に専門、治療が得意な病気、医療技術、診療モットー、趣味など、専門性だけでなく医師の性格や人柄までひと目でわかるのがファイルの特徴だ。
「全員、僕が自分の身体を任せてもいいと思える医者ばかりです」と寺下さんが胸を張る“名医”発掘の決め手は、「同級生からの推薦ですね。利害関係のない時代をともに過ごした相手が、いちばんその人の本質を見抜く目を持っていますから」と寺下さん。
さて、話は過去に戻り、寺下さんはなぜ医者の道を選んだのか
次々と襲う失明の危機、母の死、父の病気
寺下さんは和歌山県生まれで」4人兄弟の3番目。「軍隊では軍医がカッコよかったし、世話にもなった」が口癖の父親は、戦後、年の離れた自分の弟を医者にし、さらにまた、4人の息子たちも全員医者にすることが夢だった。「小さいころから医者になるんだと洗脳されてましたから、小学校2年生のときにはおぼろげながら、医者になると思ってましたね」
その一方で当時、出版されていたマンガは全部読むほどのマンガ少年で、将来は漫画家か小説家になりたいと、ひそかな夢も抱いていた。
「僕は父親が40代で生まれた子供で、学校の参観日に親が来ると、“年をとってるな。早く死なれたら困るな”と小学校の低学年のころから思ってました。ませた子供でしたからね(笑い)。それでマンガの影響もあり、医者になれば不老不死の薬を作れるのではないか。もし親父が死んでも脳だけ生かしておけば、会話ができるんじゃないかとか、バカなことぼかり考えてたんです。でも、親の死というのは僕にとって医者を選ぶうえで、ものすごいモチベーションでした」
この空想のせいなのか、東京大学医学部卒業後は、迷わず脳外科を選ぶことになる。
平隠な学生生活が一変したのは、大学6年生最後の春休みのこと。飲み屋で仲間と店の客との間で始まったケンカを仲裁しようとして客のひとりの回し蹴りが顔面を直撃。 (失明したかもしれない…・)
蹴りが顔面を直撃した瞬間、そう思った。救急車で近所の救急病院に運ばれると、
「なんだ、医学生のくせにケンカなんかして」と医者は小言をいいながら、雑に傷口を縫ってくれた。
「その縫い方じゃ、傷跡が残る」と、仲間に東大病院に連れて行かれると、担当医はすでに縫われた4針をほどき、
優しく説明しながら、丁寧に27針も縫い直してくれた。
「失明するかもしれないという不安の中でも、医者によって患者の扱いがこんなにも違うのかとすごい驚きでしたね」“激動の年”は、これだけでは終わらなかった。失明は免れたものの、その年の6月、母親が劇症肝炎で倒れたのだ。
劇症肺炎は100人中100人が助からないといわれる病気。仕事も半分に、兄弟4人は寝ずの看病を続けるが、発病から1か月半、母親は54歳で亡くなった。
「親を長生きさせたい一心で医者になつた僕のモチベーションの半分は、その瞬間なくなってしまったわけです。もう医学部を辞めると駄々をこねていたら、中学校時代からの親友が、“おまえ、何いってんだ。男が1度決めたことを、お袋が死んだからといってやめていいのか”と撒を飛ばしてくれたんです」
“激動”は母親の死後も続いた。その年の秋、今度は父親が糖尿性昏睡に陥ったのだ。その直前、父親が口にした言葉は、
「お母さんを和歌山で亡くした。だからワシを次男、三男のいる東京の信頼できる病院へ連れて行ってくれ」
再び兄弟がカを合わせ、飛行機で父親を東京まで運び、羽田空港から次男の勤務先である東京女子医大病院に救急車で撒送した。
「もし親父が死んでしまったら、お袋の死で半分失われた残りのモチベーションもなくなってしまう。そうなったら僕は、医者になれないとまじめに思いましたよ」
幸運にも、父親は数週間の入院で奇跡的に生還を果たし、寺下さんも医師国家試験に向けて猛勉強を始めた。
(1番で合格するぞ!)
「自分の失明の危機、母の死、父の病気とまさに激動の大学6年生でしたが、あの1年があったから医者としていまの僕があるんでしょうね」
その後、医師国家試験をパスし、医師としてようやくスタートラインに着いた。が、本当の困難はこれからだった。
「彼は若いころから従来の医療に対し、自分の考え方を持っていて、もうちょっと患者さんのためになる医療をしようじやないかとよく話していましたね」
東大病院内科時代の仲間で、寺下さんが立ち上げた『主侍医倶楽部』にも心療内科の医師として協力してきた現・早稲田大学人間科学科教授・野村忍さん(53)は、30年前の寺下さんの姿をこう語る。
当初、脳外科医として東大病院に勤務した寺下さんだったが数年後、内科へ移った。他の3人の兄弟が全員、外科の医師で、将来は腫瘍学をやりたいとの思いがあったからだ。
4、5人の同級生チームを引っ張って新天地の内科に移るが、教授との関係がうまくいかず悩んでいた4、5年後に身体に異変が起きた。医局の学会で司会を務めることになり、そのリハーサル中、心理的不整脈によるパニック障害を起としたのだ。
「内緒で信頼できる先輩に心電図をとってもらい、重大な不整脈ではないことがわかりました。でも、このまま東大病院に入院したら殺されちゃうから(笑い)と、親友のドクターのいた榊原記念病院に駆け込んだんです」
1週間の入院-。
「“このまま内科にいて、自分の魂をねじ曲げれば教授になれるかもしれない。しかし……”と病床でずっと自問自答してました。米国に『メイヨークリニック』という世界最高峰といわれる病院があるんですが、僕も最初は東大病院にその理想を見ていました。ところが現実は、医者になったらみんな平等で、出るものの足を引っ張る。ヒエラルキー(階層)のトップにいる教授は自分の身を守るのに精いっぱいで、とても弟子を育てる余裕はないわけです。安心を提供できる医療には、とても遠かった。それでこのままいてもいいのかと……」
寺下さんが自問自答しているとき、後輩医師のひとりが見舞いに釆た。優秀でわが道を行くタイプのこの後輩から、予想外の言葉が発せられた。「先生、逃げるが勝ちって言葉もありますよ。勇気ある撤退ともいいますが」
寺下さんはハッとなった。(よし、独立してやりたいことをやってやろう!)
「“一匹オオカミでこの先どうなるかわからんけれど、ま、なんとかなるだろう”とその瞬間、決心がついたんです。だから僕、勇気ある撤退という言葉が好きなんですよ」
1984年、寺下さんは東大病院を辞め東大赤門前に4畳半の部屋を借り、『寺下医学事務所』を開いた。その後、近くの広い部屋に移り、収入を得るため、昼間は病院で働く。夜は7時過ぎに東大病院の仲間たちが三々五々集まり、深夜まで医療のあり方について議論をかわした。
そして、東大病院を辞めた6年後の1990年、“主侍医”による医療を実践するためクリニックを立ち上げた。
「彼が自由診療で始めた16年前といえば、医療費はただ同然が当たり前の環境。周囲から冷ややかな目で見られたり、“金持ちのための医療”など と陰口を叩かれながら、それでも紆余曲折の末に軌道に乗ったのは、彼を応援したいと思う人たちがたくさんいたからだと思うんです。最近は大学病院の教授にセカンドオピニオン(診断や治療方針について主治医以外の意見)をもらえば、数万円を支払うのが当たり前の時代。本当に先見の明があったのだと思いますよ」(前出・野村忍教授)
寺下さんの親友で『主侍医倶楽部』の当初からのクライアントのひとり、スコラ・コンサルタント代表・柴田昌治さん(61)も、何度も緊急事態を助けられてきた。
「私にとって主侍医は、生命の保証だと思ってます。いま、自分の行った病院の医療がいいのか悪いのか、みんなわからないわけです。寺下ドクターの制度が広がると、医療の世界でも競争原理が働き、ダメな医者は淘汰され、医療の質を高めることになると思いますね」と、柴田さん。
寺下さんはつい最近、50代になってから博士号を取得した。そのきっかけとなったのは、尊敬してやまない友人の死だった。アルツハイマー病の救済因子“ヒユーマニン”を発見した東大時代からの友人・西本征央さん(享年48歳)は単身、アメリカへ渡り自力でハーバード大学教授となり、帰国後は慶応大学医学部教授となっていた。
2003年2月、ガン宣告を受けた西本さんは、苦しい闘病生活の中でも気迫で若い研究者や寺下さんと勉強会を開き、決して研究の手を抜くことはなかった。
意識不明になった最後の1週間、病床で西本さんはつぶやき続けた。
「俺は、後3年は生きるぞ」
しかし、その年の10月、西本さんは、あの世へと旅立っていった。遺された荷物の中から『寺下先生学位取得大作戦』と書かれたノートが見つかった。
“誇りあるカッコイイ医者”になる条件とは
病気になる前に書かれたもので、研究の進め方が細かく記されていた。「このノートには大感激でした。東大時代には“医学博士は足の裏の飯粒。取っても食えないし、取らないと気持ち悪い”と茶化して学位を取るのを放棄していました。そんな僕に、彼は研究を続けてほしいと、遺言状がわりにノートを遺していってくれたんです」
「アルツハイマーに苦しむ億単位の人を助けたい」が口癖だった西本さんの遺志は、親友の寺下さんにバトンタッチされたのだった。
『寺下謙三クリニック』では、患者はクライアント(依頼者)と呼ばれる。その理由を寺下さんはこう語る。
「患者さんというのは、医師にとって教えを請う相手であり、相手を尊敬する気持ちが大切だと思うからです」
寺下さんも、これまで多くの患者からたくさんのことを教えられてきた。
7、8年前に大腸ガンで亡くなったKさん(当時50歳)は、ケニアヘボランティア旅行中に腹痛を起こし、イギリスの病院で虫鼻炎と珍断される。ところが開腹して診ると、虫垂炎は誤診で、大腸ガンであることがわかった。間もなくガンは肝臓に転移し、医師から「もうなすスベがない」と宣告されると、古くからの友人の寺下さんを訪ねて釆た。
「テラさんに、最後まで看取ってほしい……」
とKさん。寺下さんが非常勤で勤務する病院に入院するが、見る見る肝臓ガンは進行。
しかし、はた日でわかるほど腹部が腫れてからも、Kさんは穏やかさを失わなかった。(見舞うのもつらいな……)
寺下さんは内心こう思いつつ病室に足を運び、Kさんに、「先生が笑顔で部屋に入って来てくれるだけで、うれしいのだから、大丈夫」と逆に慰められた。病気のことには触れず、趣味や旅行の話を楽しそうに話し、あるときKさんはこんなことをいった。
「いままで仕事ばかりで、ゆっくり子供たちとも話ができなかったが、この病気がよい機会をくれました」
旅行を後悔したり、イギリスでの誤診への不平を一切いうこともなく、Kさんは病気を受け入れ、静かに逝った。
「プロである私が不安そうな顔をしていたことを反省すると同時に、主侍医としては真剣さと明るさを最後の最後までいかに持ち続けるかを研究すべきだと痛感しました」
寺下さんの息子の小学校の担任だったHさんも忘れられない患者のひとりだ。口腔のガンが再発したとき、「困ったら寺下くんのお父さんのところへ行こうと思ってました」と訪ねて釆た。
一緒に専門医、ホスピスなどを回るが、結果、宣告は厳しいものばかり。つい口数が少なくなる寺下さんに、
「少しばかりの希望だけでも生きがいになります」と感謝の笑顔を向けた。
「どんなに厳しい状況でも、覚悟を決めながら、しかし、希望を持ち続ける態度が必要です。決してあきらめない心構えが医者には必要だと、その瞬間、背筋が伸びた気がしました」
医療をとおして患者に安心を提供する道は、口でいうほど生やさしいことではない。寺下さんも東京大学病院を辞めた22年前は、ハイテク技術で安心の実現を試みた時代もあった。仲間と協力して患者情報を入れたICカードを開発したり、当時の、いまとは比べものにならないほどの貧弱なパソコンを使って、全国の医者のネットワーク作りなどに挑戦していたころ、心の中で「待てよ」と引きとめる声が聞こえた。
「医療のいちばん大切なリソース (資源)は、人だと突然気づいたんです。ハイテク技術だけでは患者は幸せになれないひ昔、カバンを自転車に乗せて往診していたような、患者を丸ごと診られる、心ある医者をつくることがまず大切だと考え直しました」
行き過ぎた技術への反省から、『寺下謙三クリニック』では、“学術的”“実際的”“人間的”を基本理念に置く。
「学術的というのは、学術的・学問的に理論がしっかりしていて、探究心に富んでいることです。実際的とは、見かけや名声だけでなく、実際に役立つこと。そして人間にとってのやさしさに配慮することが、人間的の意味です」
さらに人づくりのため、若い医師や医学生の教育にもカを入れてきた。慶応大学医学部では10年前から“社会薬理学”の授業を持ち、医者の心構えや、医療現場で医者が下す“判断”の難しさを学生自身が考える機会をつくっている。そのときに必ず寺下さんが学生にいうのは、「誇りあるカッコイイ医者になれよ」だ。もちろん自らにも課している言葉だが……。
「誇りあるカッコイイ医者とは何かといえば、これは『主侍医倶楽部』の医者選びの3つの柱である。“あきらめない”“手を抜かない”“やりすぎない”に尽きます。今年の大学駅伝で、なぜ順天堂大学の難波選手がカッコよかったかというと、酸欠になりながらもゴールをあきらめなかったからですよ」
医師の専門分化が、専門の病気には詳しいけれど患者の身体全体を見ることのできない医者をたくさんつくってきた反省から最近、医療現場で、先輩が後輩を指導する研修制度が見直され始めている。
「実は僕も“スーパー医局”を作りたいんです。学閥、専門を超えて先輩が後輩を教える場であり、医師同士が交流できる場。さらに医師によい職務を紹介することができたら、医師たちはもっと安心して本業に専念できると思うんです」
55歳で医者を引退し、少年時代の夢だった小説家になると宣言している寺下さん。
“名医”が今度は筆でどんな世界を描くのか……楽しみだ。
取材・文/小清水由良
撮影/池谷彩子